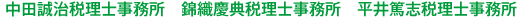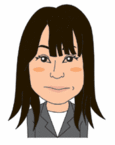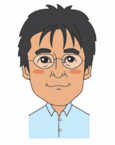- [2013.08.09]
- お客様への説明
税理士の手嶋です。

税法の条文には、その立法趣旨や制定に至った背景があります。
原則的に税法は課税の公平を最も重視しています。
その他そのときどきの政治や時代背景なども大きく影響しています。
簡単な例で言うと、役員報酬が経費になるには定期同額給与といって、
一定期間、同額の給与が支給されていることが条件になります。
原則として期中での給与の増減が認められていないのです。
ではどうして認められないのか?
それは役員報酬を決めるのは役員であり、役員が自分の役員報酬を自由に変更できれば、
法人の所得を調整することができるからです。
これを顧問先に説明するのに、単に役員報酬は変えてはいけませんでは、
「どうして?」ってことになりますが、法人の恣意性の排除及び利益操作の防止等の趣旨を
説明することですんなり納得してもらえます。
以前も書きましたが、
難しいことをやさしく
やさしいことを深く
深いことを面白く
伝えたい。
そのためにお客様への説明にはできるだけ趣旨や背景を話すように心がけています。
ただ僕は教えたがりなとこがあって、ついつい話しすぎてしまうので
あまりくどくならないように注意しています。
- [2013.08.01]
- 五公五民
税理士の手嶋です。

五公五民とは江戸時代の租税徴収で、年貢(公)と農民保有(民)の割合のことです。
収穫の半分を年貢として納め、残りの半分が農民のものです。
時と場所によりこの割合が異なり、租税の取り立てが限度を超えると、
昔なら百姓一揆が起こっていたわけです。
さて平成の日本ですが、平成27年から所得税の最高税率が
現行の40%から45%に引き上げられます。
課税所得4000万円超の部分に45%の最高税率がかかることになりました。
住民税10%を合わせた最高税率は、所得税45%+住民税10%=55%になります。
この引き上げに合わせて相続税の最高税率も55%になることが決まっています。
所得税、相続税とも最高税率部分では五公五民を超えました。
百姓一揆のかわりに、富裕層の間では国外疎開が進んでいるようです。
アジアなら、シンガポール、タイ、香港など相続税や贈与税がない国、
資産運用のキャピタルゲインに対する課税がない国などが人気のとのことです。
消費税引き上げのタイミングで富裕層への課税を強化しているのでしょうが、
限度を超えるとそれを逃れる動きも加速します。
ちなみに昭和59年以降では、昭和62年の所得税60%、住民税16%の
合計76%という税率が最も高い税率でした。
所得が1億円増えても、手残りが2400万円では何ともさみしい感じですね。
- [2013.07.26]
- 山口の山奥の小さな酒蔵
税理士の手嶋です。

先日、日本酒の獺祭(だっさい)で有名な旭酒造の桜井社長の講演を聞く機会がありました。
いまでこそ全国的なブランドになりましたが、現在に至るまでの貴重な話を聞くことができました。
近くにマーケットがない、原材料が思うように手に入らない、杜氏がやめたなどの
数々のピンチを逆手にとり、東京進出、良質な山田錦の仕入れルートの開拓、
社員による四季醸造の開始、という現在の生産体制の基盤となる変化を遂げ、
成長への道を切り拓いてきたことを話されていました。
もちろんお酒もいただきました。
純米大吟醸 獺祭 二割三分、にごり酒の発泡酒などどれも非常においしかったです。
この旭酒造、岩国市周東町の山奥にあるのですが、実は祖父母が周東町に住んでいたため、
20年以上前から存在は知っていました。
知っていたとは言っても、蔵の前を通るときに、古い建物があるな~、
酒屋さんかな?くらいの認識でした。
あんな辺鄙な場所にある会社のお酒がJALのファーストクラスで使われるようになり、
そして海外に日本酒の文化を広めていることに驚いていますが、
山口県出身の私としては誇らしい気分です。
HPによると、どうやら酒蔵を見学できるようなので、今度申し込んでみます。
- [2013.07.18]
- 不動産の共有持分について
税理士の手嶋です。

今日は不動産の共有持分についてです。
マイホームを3,000万円で取得し、支払いは夫が1,000万円、妻が1,000万円、
残りの1,000万円は同居する親が負担しました。
この家はすでに登記されており、共有持分は、夫:妻=9:1でした。
これで税務上問題ないのでしょうか?
不動産を共有名義で取得する場合の持分割合は資金の負担割合に応じて決まります。
上記の例では、夫:妻:母親=1:1:1が正しい持分割合になります。
資金の負担割合と共有持分が違うと、資金を負担した妻と母親から夫に対して
贈与があったと認定されてしまいます。
この問題のもっともシンプルな解決方法は共有持分を正しい割合に直すことです。
その他、共有持分の割合を訂正しない場合には夫と妻、夫と母親の間で
金銭消費貸借契約を結ぶ方法もあります。
ただしこの方法を選択するには、夫は実際に妻と母親に借入金を返済する必要があります。
返済が行われず、あるとき払いの催促なしでは実質的に贈与と変わりなくなってしまうからです。
親族間の借入れについては契約書の作成、通帳に返済の証拠を残すなど注意点があります。
不動産の共有持分と資金の負担割合が異なる事例は結構あります。
思いもよらない税金がかからないように注意しましょう。
- [2013.07.16]
- よつば会計の備品たち~その③~
よつば会計 森下です。
わが事務所の備品シリーズ第三弾
今回は、ウォーターサーバーをご紹介します。
事務所にあるウォーターサーバーは、赤いバーを押すと熱湯、青いバーを押すと
冷水が出る優れものです。
暑い夏には、冷水がいつでもすぐに飲めますし、熱湯もすぐに出るので、
インスタントコーヒーや紅茶もすぐに飲めます。
ボトル1本が12リットルですが、だいたい1日に1本はなくなります。
私の場合は、
 朝出勤して、第一弾でご紹介した「コーヒーマシーン」でカプチーノを飲みます。
朝出勤して、第一弾でご紹介した「コーヒーマシーン」でカプチーノを飲みます。
 お昼前には、ウォーターサーバーのお水を飲みます。
お昼前には、ウォーターサーバーのお水を飲みます。
 お昼時には、ウォーターサーバーのお水で作り冷蔵庫で冷やしてあるお茶を飲みます。
お昼時には、ウォーターサーバーのお水で作り冷蔵庫で冷やしてあるお茶を飲みます。
 午後からは、ウォーターサーバーのお湯で作ったインスタントコーヒーを飲みます。
午後からは、ウォーターサーバーのお湯で作ったインスタントコーヒーを飲みます。
 夕方は、ウォーターサーバーのお湯で作った紅茶を飲みます。
夕方は、ウォーターサーバーのお湯で作った紅茶を飲みます。
この天国のような職場環境で、驚くほど仕事がはかどります。
はかどるはずです。
多分はかどっていると思います。
きっとはかどるでしょう
事務所には、まだまださまざまな備品たちがいます。
これからも少しずつ紹介していく予定ですので、こうご期待!
- [2013.07.13]
- 払い過ぎた利息が戻ってきたら税金はかかるの?
税理士の手嶋です。

過払い金請求ってわかりますか?
消費者金融等からお金を借りて、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利の
支払いをしていた場合に、その払い過ぎた利息のことを過払い金といいます。
平成13年5月までの法定上限金利は40.004%でした。
1,000万円借りたら、金利が400万円です。すごい金額です。
これを利息制限法で計算すると金利は150万円となり、払い過ぎ部分は250万円です。
この上限金利40.004%はその後、出資法の上限金利である29.2%になり、
そして利息制限法の20.0%に変わっています。
数年前までこの過払い金請求が弁護士、司法書士に特需をもたらしていましたが、
それも今はだいぶ落ち着いてきたようです。
この過払い金請求をし、返還があった場合の税務上の取り扱いについては以下のようになります。
① 家事上の借入金の場合
過払い金・・・課税関係なし
過払い金に付された利息(以下「利息」)・・・支払いを受けた日の年分の雑所得
② 事業にかかる借入金の場合
(1)事業的規模の不動産所得・事業所得等の必要経費に算入していた場合
過払い金・・・判決のあった日の即する年分の総収入金額に算入
利息 ・・・支払いを受けた日の年分の総収入金額に算入
(2)事業的規模でない不動産所得・事業所得等の必要経費に算入していた場合
過払い金・・・必要経費に算入した各年分の所得税を修正
利息 ・・・支払いを受けた日の年分の総収入金額に算入
過払い金に付された利息については所得が生じたと考えて家事上、業務上を問わず
課税対象になっています。
家事上の雑所得の場合、給与所得者なら20万円を超える金額だと申告義務が生じますが、
20万円以下の金額なら申告義務はありません。
事業にかかる借入金で事業的規模の場合、遡る必要がなく、その年の確定申告に
反映させればよいので簡単です。
事業的規模でない場合、過去の申告につき修正申告をする必要があるため少々面倒です。
ただし、国税の時効は法定納期限から5年なので過払い金問題の時期から考えると
申告の必要はないものがほとんどかもしれませんね。
- [2013.07.12]
- 人は石垣、人は城
「人は石垣、人は城~♫」
風呂につかりながら、鼻歌でよく歌う「武田節」の一説です。
武田信玄や軍事については詳しく知りませんが、強い軍隊、騎馬隊をつくるのに
信玄が「人」に注目し、リーダーシップを取り組織経営を行っていたことが伺えます。
経営者の方とお話ししていると、様々な悩みを抱えられています。
その中で良く話題に上るもののひとつに、「人」に関することがあります。
人材の募集や給与体系などから、職員教育の問題、配置、組織の問題、モチベーション
の上げ方、そして企業のリーダーとしての職員へのかかわり方。
そこで少し、「リーダーシップ」について調べてみました。
「リーダーシップ」については、多くの経営学者、心理学者をはじめ、多くの学者、
実務家がそれぞれの理論を唱えています。また、現在も有名経営者や、スポーツ選手
などを題材にした「理想のリーダー像」みたいなものが多く出版されています。
その中で、ベースの考え方として「行動論」「適応理論」をみてみました。
学者や研究団体によって、主張は様々ですが、大まかに次のことが言えるでしょう。
リーダーの行動パターンとして「タスク志向型」(生産性向上など、業務中心で
専制的にリーダーシップをとる)と、「民主主義型」(部下と協調しながら、また、
経営に参画させながらリーダーシップをとる)があるようです。基本的には両方
備わっているのが最もよいとする考え方が多いようですが、「タスク志向型」
が良いとする学者は見当たりません。
心理学で有名なPM理論(三隅二不二博士が1966年に提唱)は集団機能を考える
中で、リーダーをP(目標達成機能)とM(集団維持機能)とに類型化しました。
Pは「タスク志向型」、Mは「民主主義型」のようなものです。この2つの機能の
強弱によって、リーダーシップを下のように4つに類型しました。
(大文字、小文字で強弱を表わします)
|
②Pm型 ・仕事に対して厳しい ・集団をまとめるのは苦手 |
④PM型 ・生産性を高めながら、集団維持をまとめる力がある |
|
①pm型 ・仕事に甘い ・部下の面倒見悪い |
③pM型 ・部下の面倒見は良い ・仕事には甘い面あり |
様々な実証研究をとおして、生産性に焦点を当てた場合、
短期的には ④>②>③>①の順で
長期的には ④>③>②>①の順で成果が上がると結論されています。
また、組織メンバーの能力が低い場合は「タスク志向型」のリーダーを、
能力が高い場合は、「民主主義型」のリーダーを配置するといった研究も行われて
いるようです。
企業経営において、「人」永遠のテーマのようですね。
「人は城」
私は、「城」に対してこんなイメージを持っています。
「城」→「人が集まるところ」→「文化が生まれるところ」→「平和を築くところ」
少し強引ですね。
人を大切にできる優しさと、城を守れる強さを持てるようにと、自分の息子の名前
には「城」という字を使いました。
我が息子、名前だけは立派なリーダーです。(2歳ですけど・・・)
- [2013.07.09]
- 平成25年路線価
税理士の手嶋です。

先週の話になりますが、7月1日に平成25年度の路線価の発表がありました。
5年連続の下落ということですが、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、平成23年分以降は
3.1%→2.8%→1.8%と下落幅が少なくなりながら推移しています。
路線価は1月1日時点の価格であるため、アベノミクスの影響は受けていません。
アベノミクスが路線価に反映されるのは平成26年です。
実体経済に良い影響を与えていれば、来年は路線価が上昇するかもしれませんが、
一体どうなることでしょう。
広島市の最高地点は“中区胡町福屋百貨店前の電車通り”となっており㎡単価は1,770千円でした。
ちなみに過去最高金額も同じ場所で、平成4年に㎡単価10,720千円を付けています。
坪3,500万円って高いですね。
平成4年と平成25年では路線価に6倍もの開きが出ています。
商業地のため特に下落幅が大きいですが、住宅地でも3分の1程度の下落はあります。
土地の価格が下がったことは相続税に大きな影響を及ぼしました。
日本の資産家は土地持ち資産家ですから土地の評価が下がれば、
相続税を納める人は減少し、税収も少なくなります。
平成27年1月には基礎控除の引き下げが決まっています。
ここまで土地の評価が下がっていなければ、基礎控除の引き下げはなかったかもしれないですね。
- [2013.07.04]
- 税理士の実態
税理士の手嶋です。

日本税理士会連合会が本年5月にまとめた平成24年度税理士登録事績というものが出ていました。
24年度資格別新規登録者数の内訳
試験免除者1423人
試験合格者1017人
公認会計士519人
弁護士52人
特別試験合格者1人
計3012人とのこと。
試験免除者とは23年以上税務署に勤務し、指定研修を受けたいわゆる国税OBです。
最近は定年退職してから登録する人が多いようです。税理士の平均年齢が上がるわけです。
試験合格者は、その名の通り試験に合格した者です。
ですが試験合格者は全員が5科目合格した者ではありません。
大学院に行くことで会計科目や税法科目を免除され、1科目あるいは2科目だけ試験を受けて
合格している者を含んでいます。
まともに5科目合格している人は試験合格者の半分いるのでしょうか?
公認会計士、弁護士も税理士登録することができます。
この人たちがフリーパスで税理士登録できることが税理士業界では問題になっており、
会計あるいは税法の試験を受けるよう税理会は意見を出しています。
ただ、この数字を見ると国税OBと公認会計士・弁護士の試験免除者の割合が約2/3って
現状はどうなのでしょう。
更に大学院による試験科目の一部免除もあるわけです。
免除、免除って、それで税務の専門家として税理士法に掲げる税理士の使命を全うできるのですかね。
こんな現状でいいのか疑問です。
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された
納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
- 2025年12月(3)
- 2025年11月(3)
- 2025年10月(3)
- 2025年9月(2)
- 2025年8月(2)
- 2025年7月(3)
- 2025年6月(4)
- 2025年5月(2)
- 2025年4月(3)
- 2025年1月(1)
- 2024年12月(4)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(4)
- 2024年9月(3)
- 2024年8月(4)
- 2024年7月(3)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(3)
- 2024年4月(3)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(3)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(4)
- 2023年7月(3)
- 2023年6月(3)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(4)
- 2023年3月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(5)
- 2022年11月(3)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(4)
- 2022年7月(5)
- 2022年6月(4)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(2)
- 2022年3月(1)
- 2022年1月(3)
- 2021年12月(4)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(4)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(2)
- 2021年6月(4)
- 2021年5月(3)
- 2021年4月(3)
- 2021年3月(1)
- 2020年12月(4)
- 2020年11月(2)
- 2020年10月(1)
- 2020年9月(3)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(4)
- 2020年5月(4)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(1)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(5)
- 2019年11月(2)
- 2019年10月(3)
- 2019年9月(5)
- 2019年8月(4)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(4)
- 2019年3月(1)
- 2019年2月(1)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(4)
- 2018年9月(2)
- 2018年8月(5)
- 2018年7月(4)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(2)
- 2018年4月(2)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(1)
- 2018年1月(4)
- 2017年12月(3)
- 2017年11月(2)
- 2017年10月(2)
- 2017年9月(3)
- 2017年8月(2)
- 2017年7月(2)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(2)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(2)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(2)
- 2016年8月(4)
- 2016年7月(2)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(1)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(1)
- 2016年1月(2)
- 2015年11月(3)
- 2015年10月(3)
- 2015年9月(3)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(4)
- 2015年5月(2)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(2)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(4)
- 2014年12月(3)
- 2014年11月(1)
- 2014年10月(3)
- 2014年9月(2)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(3)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(1)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(3)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(7)
- 2013年7月(9)
- 2013年6月(6)
- 2013年5月(4)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(7)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(4)
- 2012年12月(4)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(8)
- 2012年9月(8)
- 2012年8月(4)
- 2012年7月(6)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(1)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(1)
- 2011年12月(1)
- 2011年11月(1)
- 2011年10月(1)
- 2011年8月(2)
- 2011年1月(1)
- 2010年11月(1)